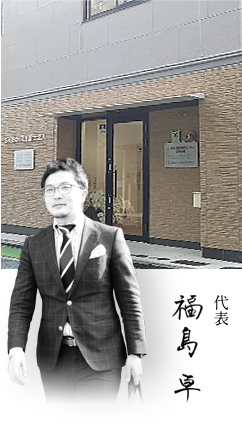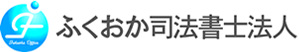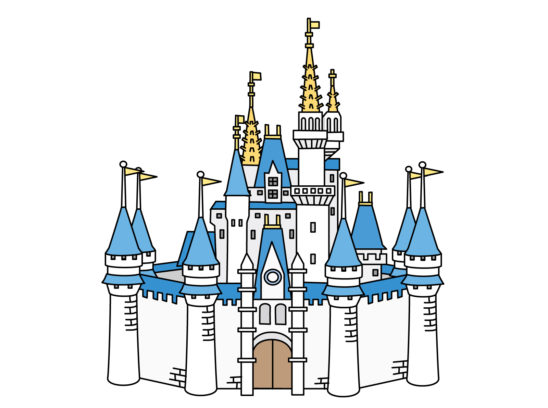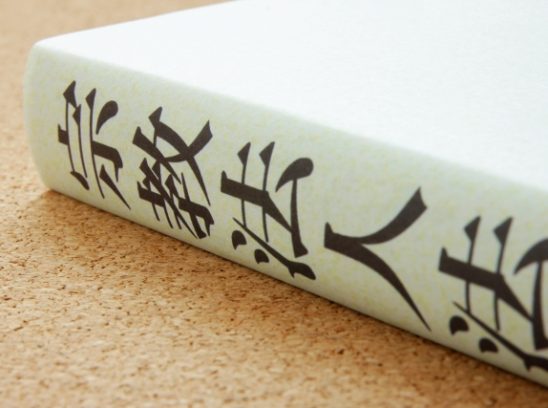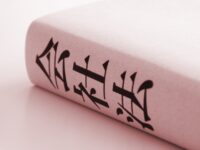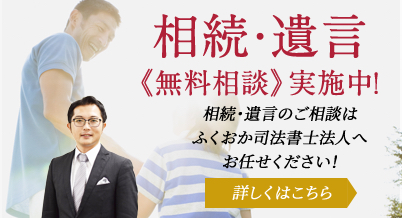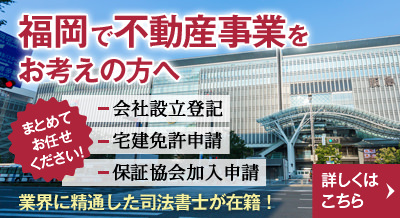複数の司法書士事務所が連件で申請する場合の不動産登記手続きについて
2018.02.01

- 早いもので1月も終わり、今日から2月スタートです。
なんかもう、今年はいつになく寒くて、早く冬が終わらんかなぁって感じです。
さて、不動産の決済の場合に、通常仲介業者さん若しくは買主さんの融資先の銀行等から
登記のご依頼があります。
その場合に売却物件に抵当権(売主さんが、不動産を購入する時に銀行等から融資を受けて
る場合)がついてる場合も①抵当権抹消→②所有権移転→③抵当権設定と、連件で1つの事務所が担当します。
しかし、売主の担保権者の銀行(売主さんに抵当権をつけてる銀行等)が、抵当権抹消の登記を
「いつも依頼してる司法書士で手続きをしたい」と、司法書士を指定してくる場合もあります。
また、買主さんが、所有権移転の登記を「いつも依頼してる司法書士で手続きをしたい」と、
これまた司法書士を指定する場合もあります。
さらに、買主さんの融資先の銀行も抵当権設定の登記を
「いつも依頼してる司法書士で手続きをしたい」とまたまた指定する場合もあります。
こうなると、①抵当権抹消はA事務所→②所有権移転はB事務所→③抵当権設定はC事務所が担当する事になり、
決済時の銀行の応接室は、人であふれかえり、誰が誰だかになってしまいます。
で、その場合にどの登記がイニシアチブを取るか?というと、やっぱり③の抵当権設定なわけで、
(まぁ融資金が出ないと売買できないですしね)そうなると、③を担当する事務所
の申請方法にA事務所とB事務所は従う事になります。
申請方法って幾つもあるの?事なんですが、大きく分けて2つですね。
書面申請とオンライン申請です。
書面申請の場合は、決済終了後に法務局で待ち合わせて、一緒に出します。
では、オンライン申請は、どうするか?なんですけど、一つのパソコンの前に集まって
順番に申請していくってわけではなく、勿論各事務所のパソコンで申請します。
具体的には、(簡単に所有権移転と抵当権設定をそれぞれ別の事務所が担当する場合で
書いていきます)まず、A司法書士に「所有権移転登記」を申請してもらいますが、
その申請情報の「その他事項欄」に「本件所有権移転の登記と、○月○日付で後に申請される抵当権移転の登記(代理人B司法書士)とは連件扱いとされたい」
と記載した情報を申請してもらいます。
A司法書士は、B司法書士にFAXなどの方法で、登記の受付番号を送信します。
受付番号を受けたB司法書士は、「抵当権設定登記」の申請情報の「その他事項欄」に「本件抵当権設定の登記と、○月○日受付第○○号(代理人A司法書士)の所有権移転登記とは連件扱いとされたい」
と記載した情報を申請します。
このようにして、異なる司法書士A・Bが連携してオンライン申請をします。
もし、司法書士間での連携がなく、互いの申請情報に、「連件扱いとされたい旨」の情報がなければ、法務局も知りようが無いので、
後の「抵当権設定登記」の申請は、「登記識別情報」といった情報が提供されていないと判断され、補正もしくは却下といった事になります。
関連サービスページ: 不動産登記
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。