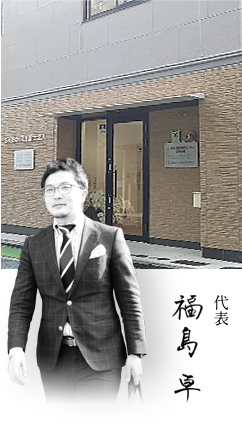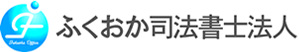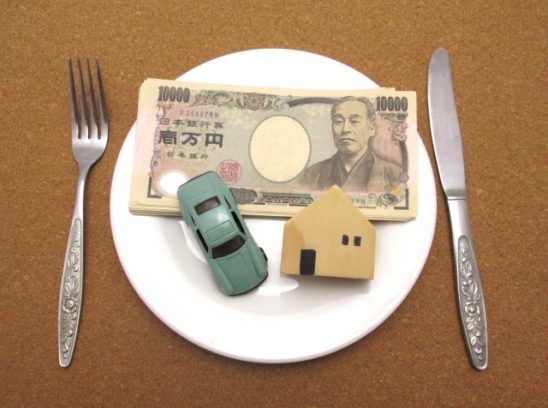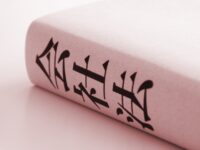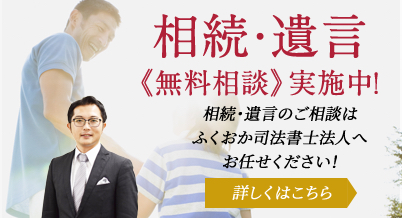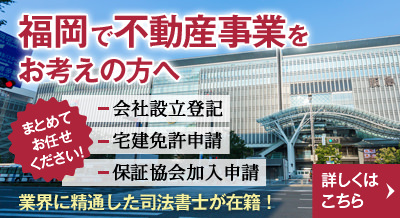登記簿謄本から登記事項証明書への変化の歴史と「事故簿」について
2019.05.29
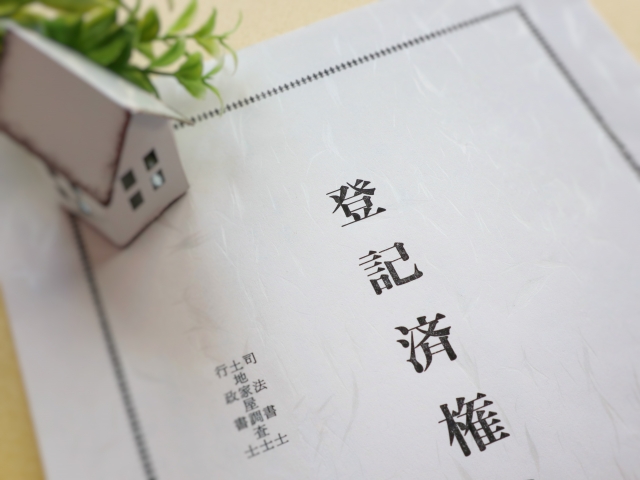
司法書士事務所の合言葉
「トーホン取って!」 「トーホン確認」
「トーホン…、トーホン…、トーホン!!!」
とにかく司法書士事務所ではこの言葉が行き交っています。
この「トーホン」とは正しくは「登記事項証明書」のことで、不動産や会社の情報が記載されています。
ではなぜ、「登記事項証明書」を「トーホン」と呼ぶのでしょうか?
今回はその歴史を紐解いて行きたいと思います。
「トーホン」と呼ばれる理由は「登記簿謄本」の名残
登記記録に記録された事項の全部、または一部を証明した書面を、「登記事項証明書」といいます。
今ではデータで管理されていますが、昔は「登記簿」と言って「紙」で管理されていました。
ですので、取りたい土地を指定すると、登記簿からその部分を(バインダーで綴ってある)法務局の人がはずしてコピーをして、認証(印鑑を押す)をしてたんです。
だから、「登記簿謄本」(謄本→原本の内容をそのまま全部写しとった文書の意味)と言われていました。
この登記簿に書かれている内容は現在と同じです。しかし、大きな違いはその不動産の登記簿は、その不動産の管轄の法務局にしかない、ということです。紙ベースでの保管はその点が大きなデメリットです。
今では、全国どこの法務局でも、取りたい不動産の登記事項証明書をとることが出来ます。
ここまでは基本の基本。それでは司法書士ならではの登記簿謄本のコンピューター化における黒歴史!?をご説明します。
業界用語「事故簿」の正体
登記簿謄本がデータ化され、全国どこからでも取得可能な「登記事項証明書」となりました、
と先述しましたが、全ての不動産がデータとして保存されているか?というとそうではないのです。
え?じゃあ漏れがあるの?ということになりますが、
実はその通り、コンピュータに移行する作業の中でどうしても移行できない不動産が出てきたのです。
例えば、
「マンションの敷地の持分の分子を全部足しても、1にならない」
「判読出来ない文字がある(昔は手書きだったりだから)」
などです。
このような不動産を正確には、「改製不適合物件」と言いますが、業界用語では「事故簿」と言います。
「改正不適合物件」の取引時に知っておくべき権利証事情
コンピュータ化に伴い変化したのは登記簿謄本だけではありません。
不動産登記で最も重要といえる「権利証」も以前のものとは全く違うものになっています。
コンピュータ化以前は、登記申請の際に「申請書副本」を添付し、申請書副本に「受付年月日及び受付番号」朱印が押され登記が完了すると「登記済証」となって法務局から発行されてました。
この「登記済証」のことを「権利証」と呼びます。
それが、コンピュータ化に伴う不動産登記法の改正で、「登記済証」から「登記識別情報」に変わりました。
「登記識別情報」は不動産一つ一つに12桁のアルファベットと数字の暗証番号の記載された紙が交付されます。紙が交付されますが、あくまでも記載されている暗証番号が権利証となのです。
それによって、今まで紙でしか申請できなかった不動産登記が、オンライン申請という,情報を送信して、申請できるようになりました。
では、データ化されなかった「改製不適合物件」もオンライン申請が出来て「登記識別情報」が交付されるのでしょうか?
答えは、NO!です。
この「改製不適合物件」についての登記申請は、データ化されていないので、
オンライン申請をすることができないので「紙」で申請をすることになります。
そして、コンピューター化されていないので、登記識別情報も発行されません。
故に、「改製不適合物件」について登記申請をする際は申請書副本を添付しなければなりません。
そして、昔のとおりの「受付年月日及び受付番号」の押印された登記済証が発行されます。
これは、申請書副本なんて作ったこともない司法書士が大多数となる近い未来、司法書士業界を困惑させる忌忌しき事態となりそうです。
そんな時も、余裕綽々で対応できる格好いい司法書士になりたいものです。
この記事が、初めて「改正不適合物件」の取引をすることになってドキドキしている同業者のお役に立つことが少しでもできれば嬉しく思います。
関連サービスページ: 不動産登記
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。