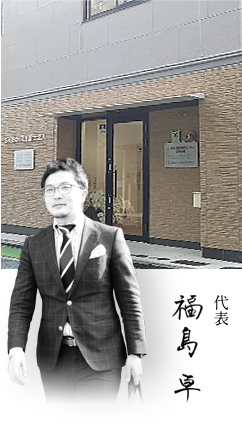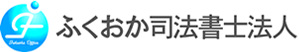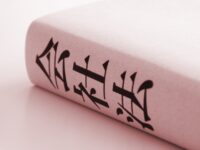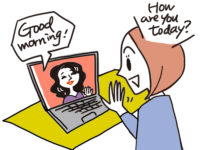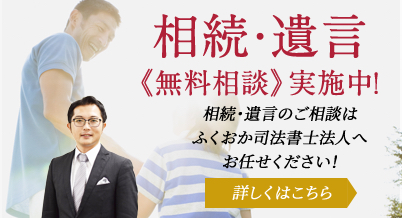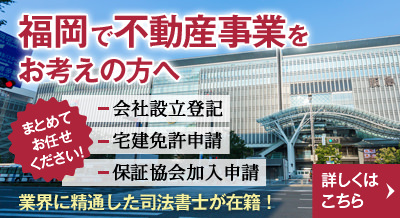持ち株数は半分こで大丈夫?平等という名の落とし穴
2022.09.29

今朝、めでたくエアコンが直りました。
エアコンの冷たい風が嬉しすぎて舞い上がってるI氏に冷房ガンガンにされて、
体温調節機能が故障している私は、早くも凍えています。
寒すぎてそっと足元のヒーターをつけたら「ピッ」という音が高々と鳴り、
すかさずS氏から「室内温度が狂うからヒーターつけたらあかん!」と物言いがつきました。
しょうがないから毛布をかぶって仕事してます。
複数人が同じ部屋にるとなかなか難しいですよね。
さて、複数人といえば、
スタートアップ企業やベンチャー企業で、複数人で起業したいというお問合せが増えています。
複数人で会社を起業する場合に問題となるのが持株比率です。
発行済み株式に対して、誰が何株持つの??ということですね。
よく考えて決めたのなら問題ありませんが、
一緒に企業するし、平等な立場で半分こにしよう!くらいで決めてませんか?
本当に半分こで大丈夫ですか?
会社設立時の資本金と持ち株数
株式会社を設立するときに決めることの1つに
・資本金
・発行済み株式数
・発起人(資本金を出資する人)
といったことがあります。
現在の会社法では資本金がいくらなどの決まりはないので、
自由に決めることができます。
例えばこんな場合。
資本金:300万円
発行済み株式数:300株(1株1万円)
発起人:A150万円出資⇒持ち株数150株
B150万円出資⇒持ち株数150株
これが「半分こで平等」というやつで、
資本金を半分ずつ出し合って、発行済み株式の半分ずつを持っている状態です。
これがどういうことかきちんと理解した上でこうしているのであれば、全く問題はありません。
後は会社設立に向けて突き進むのみです。
どういうことかって?こういうことです。
株式と議決権
会社を1人で設立したり、身内で設立するとあまりピンとこないかもしれませんが、
株式を持つということは、その会社の株主となり株主総会での議決権があるということです。
因みに株主には次のような権利が与えられます。
1.剰余金の配当を受ける権利
2.残余財産の分配を受ける権利
3.株主総会における議決権
株主総会における議決権があると一体どうなるのでしょうか。
議決権があるとどうなる?
株式会社の基本的なルールは定款で定めることになります。
例えば、会社名、目的、本店所在地、役員の任期、機関構成、事業年度、
株式の譲渡について、株主総会や取締役会の招集・決議方法・議事録の作成についてなど、
それほど複雑な機関構成をしていない会社でも一般的な定款の条数は30-40条くらいにはなります。
まず、この定款の内容を変更したい場合に株主総会の決議が必要となります。
会社のルールを変更するなら、会社の持ち主である株主の賛成が必要だよね。ということです。
この定款変更は株主総会の特別決議が必要です。
特別決議があるからには、普通決議とか特殊決議といった決議方法まであります。
株主総会の決議要件
例えば、一般的によく使われる「特別決議」と「普通決議」はこんな感じです。
特別決議
①議決権の過半数を有する株主が出席し
②出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要
普通決議
①議決権の過半数を有する株主が出席し
②出席した株主の議決権の過半数の賛成が必要
②に注目すると、特別決議で「3分の2以上」普通決議でさえ「過半数」の賛成が必要です。
半分こって何がまずか何となく見えてきたでしょうか。
半分こだとこうなってしまう
発行済株式:300株
A:150株
B:150株
例えば、上記のような持株比率の会社で、Aは新たな事業を始めようと思い事業目的に追加をしたいと思いました。
目的は定款の絶対的記載事項なので、追加したい場合は定款変更が必要です。
定款変更するためには、、株主総会で特別決議が必要です。
AとBの意見が一致していれば何も問題ありません。
しかしBが反対した場合どうでしょうか。
Aのみの持ち株数では3分の2に及ばず目的追加はできません。
他にも、例えばBが取締役になっていて
経営方針が合わないので解任したい!
といった場合には、株主総会の普通決議が必要です。
Bは当然この決議に賛成するはずもなく、
Aの持ち株数では「過半数」をクリアできずこれも断念せざるを得なくなります。
結論
起業するとき、株式半分こは結構危険です。
あまりお勧めはできません。
株式を持つということは会社の重要な意思決定に係わるということです。
何が正解かはその会社で異なるかと思いますが、
後悔のないようにしっかり話し合って決められてくださいね。
会社の登記はふくおか司法書士法人までお問合せください。
関連サービスページ: 商業登記
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。