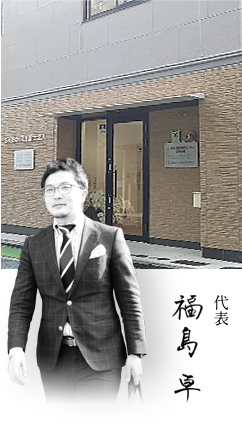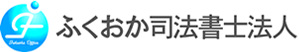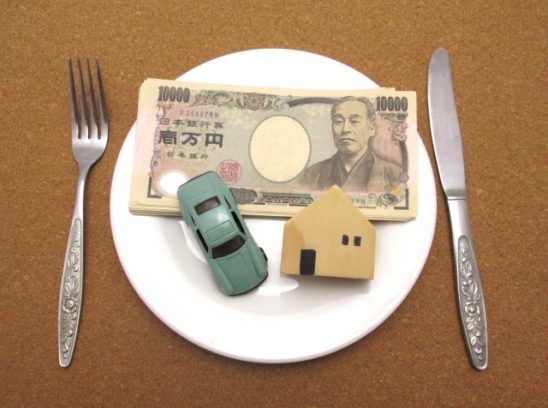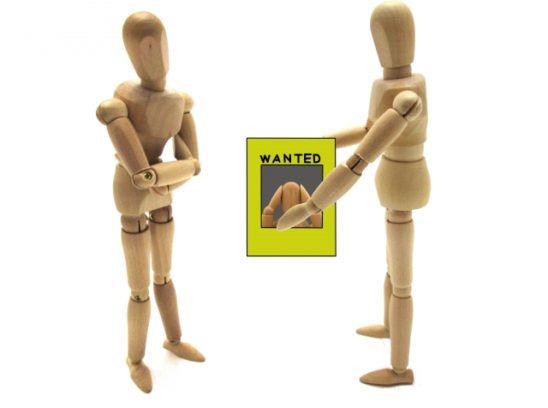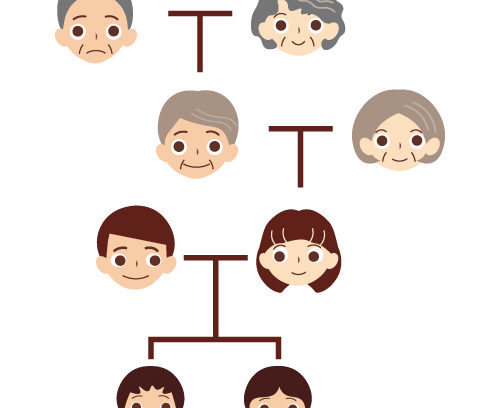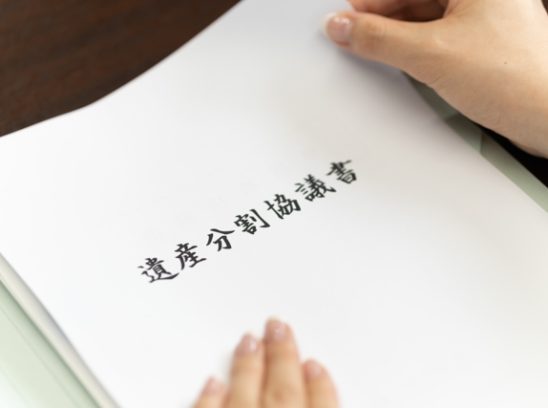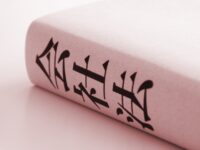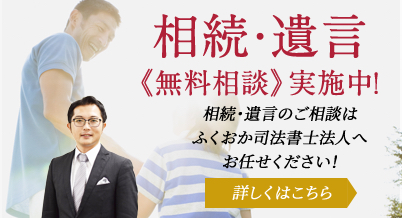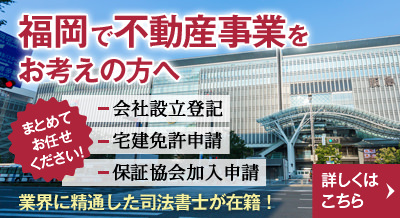遺産分割協議がまとまらない場合の解決方法

遺産分割協議のむずかしさ
家族の死。
それは、誰の人生にも起こる最も悲しい出来事でしょう。
自分が相続人になる程の近しい人間の死であれば、心に折り合いをつけるのも簡単なことではないでしょう。
しかし、現実は厳しい。
折り合いをつけるべきは、心だけではないのです。
故人が遺した財産をどう分けるのか。それを相続人全員が納得する形でまとめなくてはならないのです。
正直、どんな話し合いでも話し合いに参加した全員の意見が一つにまとまる、なんて方が稀でしょう。
それが、利害関係が対立する問題であればなおさらです。
遺産分割がまとまらない、ということは実際珍しくないことなんです。
遺産分割協議がまとまらない場合の解決方法は?
話し合いを重ねたが話がまとまらなった、
相続人が不仲で。そもそも話し合いが出来なかった、
そんな場合、家庭裁判所に「遺産分割調停の申立て」をします。
遺産分割調停での話し合い方法について
遺産分割調停では、全くの第三者である調停委員が間に入って話を進めます。
調停委員は通常男女1名ずつで、現役を引退された比較的高齢の方が多いです。
私だったらこういう場合、同性で、自分より人生経験もあり、懐が広く優しそう、という印象の方であれば、なんとなく素直に話が聞ける気がします。
自分たちで意見がまとまらなかったから調停になっている訳なので、裁判所もそういう方を調停委員に選んでいると思います。因みに、遺産分割調停では、調停委員にも法律的知識が必要になりますので、基本的には弁護士資格を保有している人が選任されます。
相続人間で顔を合わせると、つい感情的になってしまう、ということもありますよね。そのため、調停では、それぞれ個別に調停委員と話をします。
これなら、冷静に話ができて、面前では言えない本当の気持ちなども伝えられて、話がまとまりやすいのだと思います。
調停前置主義について
話し合いがまとまらず、頭にきて
「もういい!!裁判だ!!!」
と鼻息を荒くする。
こんなことは家族間でもあることだと思いますが、
家庭裁判所の事件では、通常「調停前置主義」と言って、訴訟を提起する前に調停をしましょうね、という決まりがあります。
これは、家族での争いは、今後の人間感関係にも影響するので、まずは話し合いでの解決を目指しましょう、というものです。
こういう決まりをみると、法律にも血が通っているんだな、と感じます。
遺産分割についても、まずは調停をすることになります。
但し、遺産分割審判の申立は、訴えには当たらないので調停を申し立てる前に遺産分割審判の申立を行うことは可能ではあります。その場合でも、裁判所の判断でまずは調停に回されることが一般的です。
遺産分割調停でもまとまらない場合、遺産分割審判へ移行
遺産分割調停で調停委員の方がなんとか話をまとめようとしてくれも、まとまらないものはまとまらない。
それが現実、という場合もあると思います。
それはそれで仕方がない。そうなれば、もう誰かが独断で決めるしかありません。
そうです。それを決めるのは、裁判官です。
審判は判決とどう違うの?
一般的に、裁判だ!となれば、最終的にくだされるのは「判決」ですね。
ただし、今回は審判です。
それでは、判決と審判の違いをみまみましょう。
判決…裁判官は原告・被告の主張及び提出された証拠のみに拘束され判断します。法廷は公開されています。
審判…当事者の主張や証拠以外に、家庭裁判所調査官の行った調査結果等の資料に基づいて判断を下します。
法廷は非公開です。
まとめ;遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を申し立て調停委員が間に入って話し合いをします。それでもまとまらない場合には、遺産分割審判に移行し、最終的に裁判官が様々な証拠に基づき分割方法を決定します。
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。