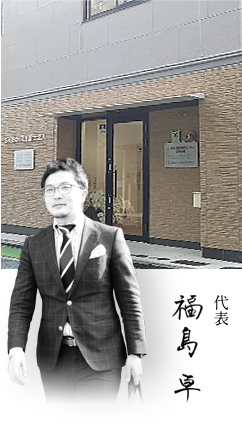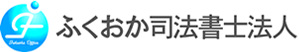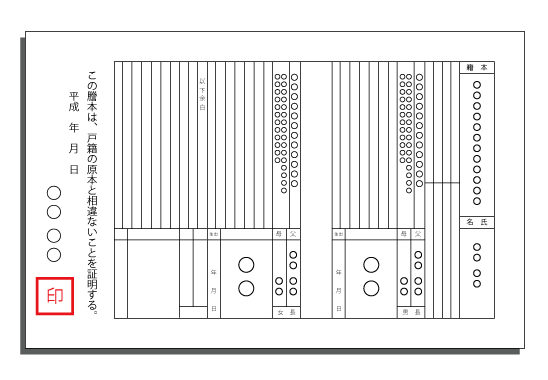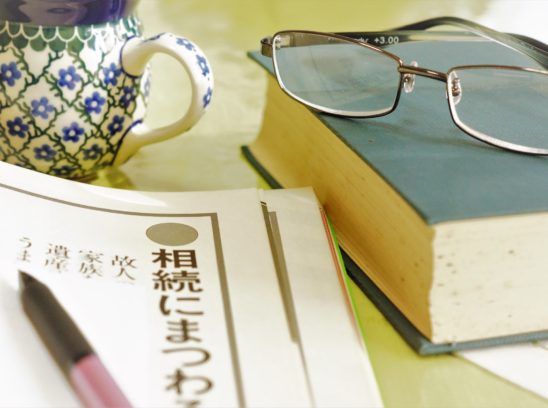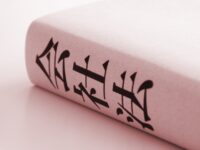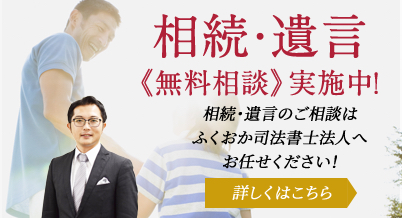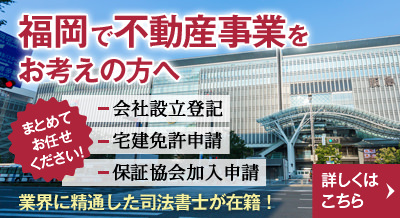遺言書 作っておいたが みつからず (季語なし)
2019.01.31
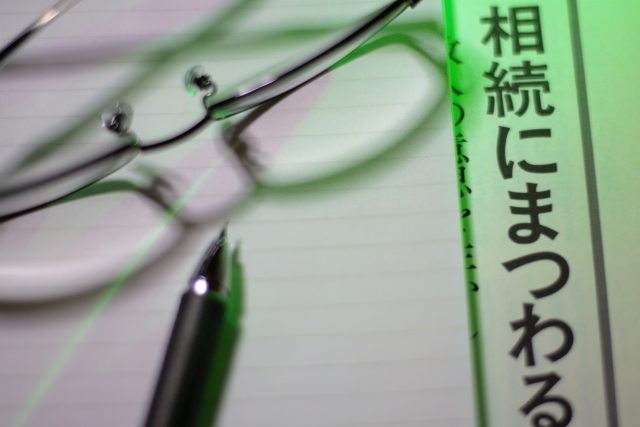
今までの自筆証書遺言は保管場所が問題でした
遺言書 作っておいたが みつからず (季語なし)
そんな俳句があの世で流行っていないことを祈ります。
遺言書は、故人の大切な意思であり、遺された家族のとっては唯一無二の大切な存在であるはずです。
それなのに、今までの自筆証書遺言の制度は「保管場所の定めがない」という不備ともいえる状況でした。
それが、今回の民法改正により、我々司法書士に縁深い「法務局」で保管されることとなりました。
法務局、と言えば我々の出番!!と鼻息荒く構えてしまいますが、自筆証書遺言の保管は「本人確認」が非常に重要となりますので、自ら出頭して行わなければなりません。何か、難しそうだな、と我々司法書士に申請を依頼されても残念ながらお受けできません、、残念です。。
自筆証書遺言を法務局で保管、証明する方法
法務局に申請なんて難しそうだな、と思われた方、安心して下さい。私が丁寧に説明します。
ご自身で書いた遺言書を封をせずにご自身の管轄の法務局に持参し、必要事項を記入した申請書を添えて提出して下さい。
厳格な本人確認と簡単な形式面の審査が行われます。
丁寧に、と言いましたが、たった2行で説明できるぐらい申請自体は簡単に出来そうです。
提出された自筆証書遺言は原本と画像データが保管され、遺言者はその閲覧を申請することが出来ます。
「ご自身の管轄の法務局」とは、住所地または本籍地を管轄する法務局、所有する不動産を管轄する法務局、すでに遺言書を保管している法務局、となります。
この際に手数料が必要になりますが、現時点では詳細は決まっていません。しかし、数千円程度になると言われていますので、費用の負担は大きくなさそうです。
相続人は、遺言者の死後、遺言書情報証明書を請求することができ、遺言書原本の閲覧を請求出来ます。
更に、この請求があったときは、他の相続人に対し通知がいくことになっています。
自筆証書遺言の保管制度のメリットとは?
-
遺言書の改ざんや隠蔽の恐れがなくなる…これにより相続人間の争いも減るでしょう
-
遺言書が見つからない可能性が低くなる…「遺言書はあると聞いていたが場所が分からない」ということがなくなる
-
遺言書の存在を相続人に伝えやすくなる…秘密が守られ改ざんの心配もないので、遺言書の存在やその場所を隠す必要が減ります
-
検認手続が不要…これは大きなメリットです!!今までは検認作業なしに遺言書に基づいた相続手続きは出来ず、時間も費用も掛かりました。
-
撤回は無料で出来る…遺言書を作って法務局に保管までしてもらうとなると、後で気持ちが変わったら大変そう、とつい後回しちゃいそうですが、安心して下さい。撤回は可能です。
上に挙げただけでも今回の遺言書保管制度は大きなメリットがあります。そうなると、遺言書にわざわざ高いお金を払って公正証書遺言を作る必要はないかな?と思う方も多いと思います。
法務局で保管する自筆証書遺言と公正証書遺言、専門家はどちらを勧める?
そんなにメリットも多くて、簡単に出来るなら、公正証書遺言より自筆証書遺言の方がいいのでは?と思われた方も多いかもしれませんね。
私も、その手軽さと、自筆証書遺言特有の改ざんや隠蔽などの不安が解消された点、費用が安く撤回は無料で出来ること、を考慮すると、内容が複雑でない限りにおいては、自筆証書遺言を法務局で保管されることをオススメします。
公正証書遺言は費用が高いうえ、証人も必要ですので、敷居が高いのが現実です。
それでも、法律の専門家である公証人が内容を精査するので安心感は抜群です。
その点では、法務局での審査は形式的なものに限るとされていますので、後々トラブルとなる可能性は公正証書遺言に比べれば高いと思います。。
また、法務局での申請は本人に限りますので、様々な事情で本人が法務局まで行けない場合には、出張制度のある公正証書遺言の出番となることでしょう。
では、早速、法務局に遺言書を持っていこう!と意気込んで下さった方!有難うございます。
しかし、遺言書保管法の施行は平成32年7月10日(金)となっておりますので、その間にじっくり遺言書の作成をされるのもいいですね。
ふくおか司法書士法人では遺言書の作成について、セミナーや個別相談会も行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
関連サービスページ: 相続・遺言
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。