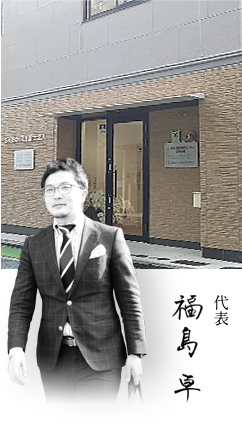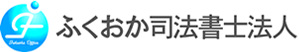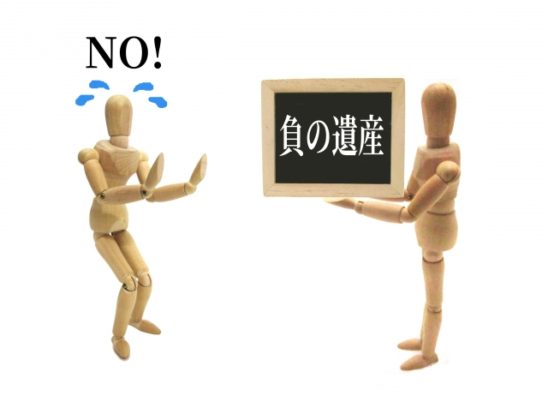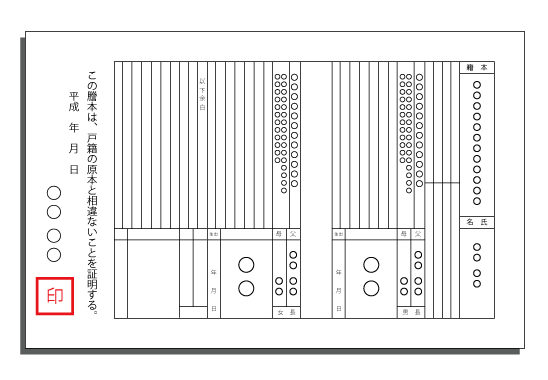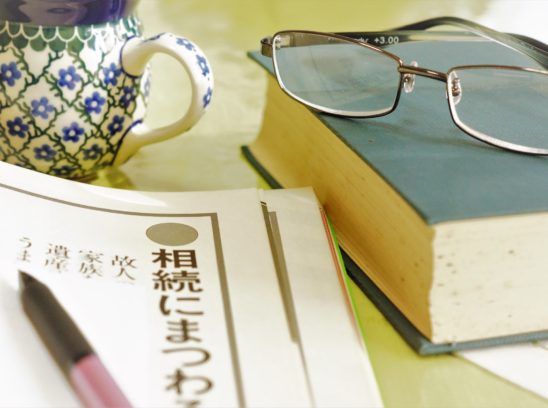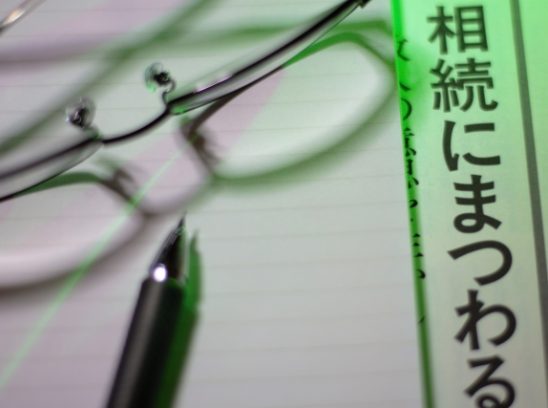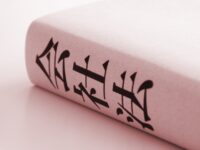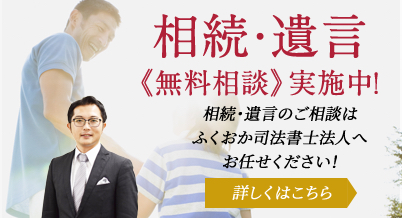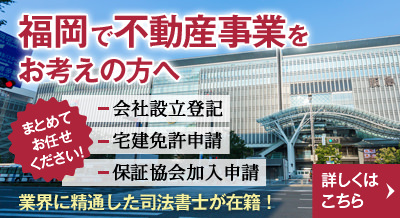相続の順番
2017.02.03
こんにちは、島崎です。
今日は、「節分」ですね。「鬼は、外ぉ~、福は内ぃ~」です。
調べてみますと、節分とは各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のこと
で、「季節を分ける」という意味があるそうです。
季節の始まりことに、節分があるんですね。(フムフム)
昔の暦では立春が一年の境目とされていたそうで、(今でいう大晦日のようなものなのかな?)
そのなごりからか江戸時代以降は特に立春の節分を指す場合が多いそうです。(なるほどね)
あと、節分って必ず2月3日って思いがちなんですけど実は違っていて、時折、2日になったり、4日になったりすることもあるみたいです。
節分といえば豆まきなんですけど、最近は「恵方巻」を食べるのが流行ってるみたいですね。
「恵方巻」も調べてみると、節分の時に恵方巻きを食べるのにもちゃんと意味はあって、「福を巻き込む」と言う願いがあるそうです。
恵方巻きは七福神にならって7つの具材を入れて作るのが、本来の形で、切らずに丸かぶりするのは「縁が切れないようにする」ためなのだそうです。
なるほどですなぁ~、息子くんに自慢してきかせてみようかな。
「学校から帰ったら、お母さんと恵方巻を作るけんね、お仕事頑張って、楽しみに帰ってきてね。」って登校する時に玄関で言ってました。
丸かじりなので、食べ切るまで一切誰もしゃべらない、シュールな時間が過ぎていくんでしょうけど・・・・。
さてさて、登記のお話ですが、最近相続手続きのご依頼が多々ありまして、せっかくなので少し相続登記のお話をば。
恐らくは、司法書士の仕事の中でも皆様になじみのある登記の一つなのではないかと思います。
しかしながら、奥が深い登記でもあります。
テレビや小説等で、相続を扱った題材も数多くありますし、興味がある方もいらっしゃる
と思います。まぁ、テレビや小説等で題材の中心は、「私は相続できるのか?」だったり、
「○○が死ねば、私だけが相続人」ですが・・・・。
でも、意外と相続登記で難航するのが誰が相続人なのか?ってことで、あながち
小説のトリックや真犯人の動機の解明と通じる感じもなきにしにもあらずなんですが。
ということで、1回目は、誰が相続できるのか?という「相続の順番」について
少し触れたいと思います。
遺産を相続する順番は法律で決められています。(法定相続)
法定相続人は血族相続人と配偶者になります。
「相続の順番」は、まず前提として配偶者は常に相続人になるということです。
例えば、Aさん(夫)とBさん(妻)が夫婦で子供がCでAさんが亡くなった場合
①BさんとCさんが相続人となります。
奥さんと子供たちでお父さんの遺産を相続するという、一番ベーシックです。
ところが、全ての家庭がそうではないので、色々と奥が深くなってくるのです。
②AさんとBさん夫婦に子供がいない場合も当然ありうるわけで、その場合に
BさんとAさんの父母が相続人となります。
③ところが、当然Aさんの父母が無くなってる可能性が当然高いわけですから
そうなると、BさんとAさんの兄弟姉妹が相続人になります。
ね、ちょっと奥がふかくなってきたでしょう?
でも、②のケースも父母は、無くなっても祖父母が健在の場合もあり得るわけで
(そうなると、祖父母が相続人になります、但しAさんより父母が先に亡くなってれば)
ね、結構奥が深くなってきたでしょ?
取りあえずは、今日はここ迄です。
次回のブログには、さらに色々なケースを見ていこうと思います。
関連サービスページ: 相続・遺言
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。